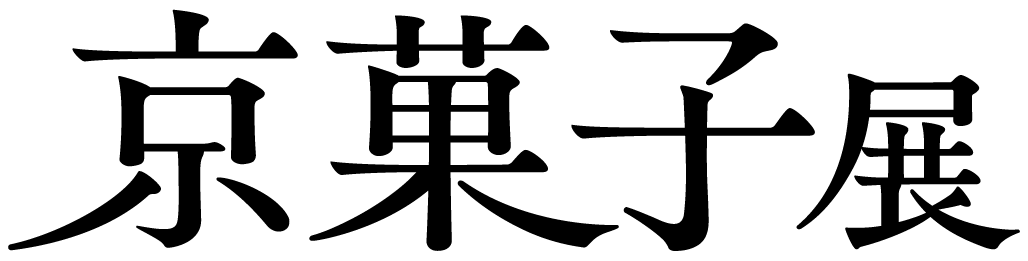
2025年展覧会「小堀遠州と松花堂昭乗」審査員講評

熊倉 功夫MIHO MUSEUM館長
小堀遠州と松花堂昭乗というむずかしいテーマをよくこなした作品が多く感心しました。またテーマからくるのか全体が京菓子のオーソドックスなスタイルに外れることなくとても心地よく審査いたしました。
作品のレベルも高く、そのまま商品として通用すると思われます。
今後の京菓子のあり方を考えさせられます。従来の素材にとらわれず、新しい素材を用いる例は今回はありません。これから両者の領域を往来する必要があるかと思います。

家塚 智子宇治市源氏物語ミュージアム
館長
京菓子展の今年のテーマは、「小堀遠州と松花堂昭乗」ということで、どのような作品と出会えるのか、とても楽しみでした。
これまでの『万葉集』『枕草子』『源氏物語』『徒然草』、そして禅は、文字通り、文章、テキストを読むことからはじまりますが、今回は、茶の湯にかかわりの深い人物がテーマであることから、ふたりに縁のある茶室や庭、そして美術工芸品なども含め、親しみのあるテーマだったかもしれません。深く掘り下げた作品がある一方で、似たような印象をうけるものまで、二極化している印象を受けました。作品が一堂に会したとき、「緑」系が多いのは、お茶、庭などからの着想でしょうか。
昨年に続き、実作部門では、意外なお味が多く、いただいて楽しかったです。決して奇をてらうのではなく、お味や素材にもこだわっていたことも魅力的です。
小堀遠州、松花堂昭乗と、京菓子を作る人たち、京菓子をいただく私たちが、京菓子を愛でつつ、対話できる…… それがこの「京菓子デザイン公募展」の魅力であり、強みだと思います。
「京菓子デザイン公募展」、そして京菓子のさらなる発展に期待します。

笹岡 隆甫華道「未生流笹岡」家元
『小堀遠州と松花堂昭乗』、難しいテーマに対し、皆さんが独自の解釈で向き合った意欲的な作品が並んだ。庭園の景色を映した写実的な作品から、二人の人物に想いを馳せた情緒的な作品まで、今年も幅広い作品が見られたのが嬉しい。
京菓子デザイン部門は、より自由で抽象的なデザインが多く、職人の方が苦労して仕上げてくださる過程も見ていておもしろい。入選者と菓子職人のコラボレーションを楽しんでいただきたい。
茶席菓子実作部門は、丁寧な仕事をされているものが多く、毎年、全体のクオリティの高さに驚かされる。もちろん意匠も大切だが、口に含むものだから、味や食感に工夫を凝らしたものに興味を惹かれる。

鈴木 宗博菓子研究家
今回も多くの良い作品を見せて頂きありがとうございます。
毎回難しい題にも関わらず、素晴らしい作品が集まると言うのは、菓子に対する熱い思いを持った方々が多く居られる事と感動いたします。
インタビューでもお答えいたしましたが、過去のタイトルである、「徒然草」「枕草子」「源氏物語」などは、文中からイメージを読み取り、菓子で表現すると言う形でした。
「小堀遠州と松花堂昭乗」は、人物像からイメージして菓子を作るという、いつもと少し違った感じがあったのではないかと思います。
今回の作品には、過去にあった奇抜さは無く、落ち着いたデザインが多く見られ、遠州と昭乗が茶道や書、庭園と言う共通点を持っていた事もあり、茶会ですぐに使えるデザインの菓子が大半を占めていると感じました。

廣瀬 千紗子同志社女子大学
名誉教授
今年のテーマは、時代が大きく変わる節目に、多彩な才能を発揮し、歴史に残る多くの仕事を成し遂げた二人の偉人、小堀遠州と松花堂昭乗である。片や武士、片や学僧。出自の異なる二人の「ものがたり」は、どのようにして小さな京菓子という形に収まるのだろうか。なかなかの難題だったと思うが、楽しみでもあった。結果は、全部門あわせて631点もの応募があり、コンセプト欄には、さまざまな想いが述べられていた。庭あり、書あり、茶室あり。二人の親交、それぞれの美意識。なかには音と静寂、茶室に差し込む光、という繊細な感覚に訴えるものもあり、京菓子が洗練された表現媒体であることが、あらためて示されたと思う。
さて、応募作品には斬新な色と形を追求したものと、伝統的な形のなかに新鮮なコンセプトを込めようとしたものがあるように見受けられた。また、一見伝統的なようで、遊び心がひそむ変わり種もあって、面白さの要素も表現の幅を広げているようであった。
部門ごとの審査の段階では、大きく票が割れる場面があった。テーマが多彩な広がりをもち、完成度の高い作品が競われたため、優劣がつけがたく、受賞作は僅差の結果である。
京菓子に最もふさわしい場所は茶室だと思うが、現代の生活では、それもなかなか難しい。むしろ、京菓子を通じて茶室の空間をイメージしているのかもしれない。そこでは、京菓子が仲立ちとなって、亭主と客、客と客との通じ合う世界を作っており、今回もそういう作品が高評価を得たようである。

西脇 隆俊京都府知事
今回初めて審査に参加させていただきましたが、「小堀遠州と松花堂昭乗」という、それぞれ深遠な思想と多数の功績を収められたお二人がテーマだったため、作品制作は非常に難しかったのではないかと思います。その中で、テーマのお二人を作品として表現しようと、様々な工夫が施された素晴らしい作品の数々にとても感銘を受けました。
京菓子というのは、京都の幅広い文化を構成する重要な文化の1つです。お菓子だからといって、ただ単に、食べるだけという訳ではなく、見た目を楽しみ、込められた想いやテーマを読み解くという営みから成り立っています。この「見た目」「込められた思想」「味」という観点から作品を磨き上げていくためにも、このように発表して審査する場があるということは非常に意味があることだと考えております。
また、今回、京菓子の「今」の形を作り上げてきた菓子職人の方だけでなく、学生をはじめ普段は京菓子に直接関わっておられない方からも多くのご応募がありました。京菓子への関わりの深さに限らず、多くの方に京菓子の魅力を知っていただくきっかけになるという点も、非常に重要なことと思います。

松井 孝治京都市長
今年は昨年と比較してとても上品な作品が多く、それぞれに目を奪われました。試食においても、どれも本当に甲乙つけがたく、素晴らしい作品の数々でしたので審査が大変難しかったです。「小堀遠州と松花堂昭乗」というテーマでは、どちらのどの切り口を取り上げるかによって、全く違う表現になっていました。プロの職人だけではなく、若い学生も多く出品されており、今回のデザイン部門では、学生の作品が審査員の中で高い評価を得ていたことが印象的でした。それぞれがいろんな角度からテーマを捉えて、京菓子を制作するこのような京菓子の公募展は他に類を見ないもので、京都が誇る「京の菓子文化」を次世代につなげる素晴らしい活動だと感じています。
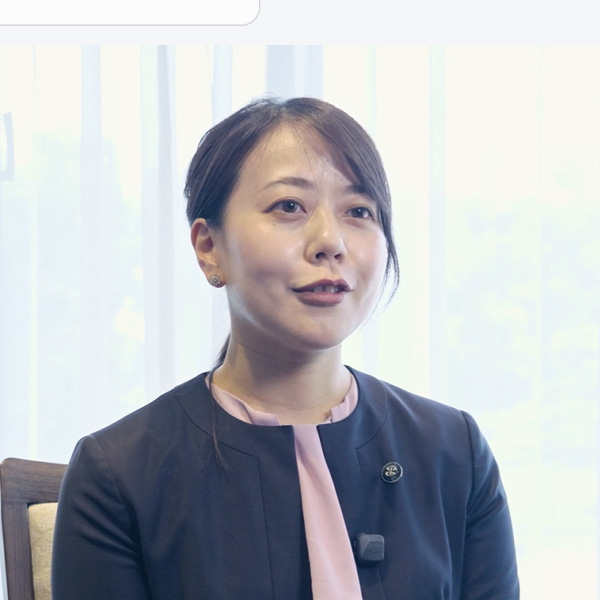
川田 翔子八幡市長
京菓子の魅力はなんといっても、たったひとさらの上に、繊細な季節感や自然への賛美、伝統行事や歴史といったテーマを表現し、見る者へ雄弁に語りかける無限の可能性ではないでしょうか。その「ころん」とした見た目の控えめな可愛らしさとは裏腹に、茶席の亭主からそのご由緒やテーマをお聞きしながら向き合うことで、お客様をひろい空想の小旅行へ連れてゆく。京都を語るうえで欠かせない「茶文化」、そのシーンに欠かせない役者が「京菓子」であると思います。今回は時代の大きなうねりとともに、「茶文化」を更なる成熟に導いた立役者のひとりである小堀遠州と、茶道においてその弟子であり、寛永の三筆と呼ばれた石清水八幡宮の社僧、松花堂昭乗をテーマとしていただきました。特に松花堂昭乗は京都八幡の地において、小堀遠州とともに設計したと伝わる壮大な懸け造りの空中茶室「閑雲軒」のほか、名前の由来ともなった庵「松花堂」など、京都に花開いた茶の湯文化の一角を担う様々な文化的遺産の足跡を遺しています。
この度の作品展では、どの作品も真摯かつ丁寧に「小堀遠州と松花堂昭乗」に向き合っていただいていることが伝わってまいりました。物語のあるお菓子「京菓子」を通し、このように京都の様々な文化の足跡について数多くの参加者様に探求いただく機会を設けてくださったことに、心より感謝申し上げます。
参加者の皆様、それぞれの素晴らしい物語をありがとうございました。

野﨑 貴典古典の日推進委員会
ゼネラルプロデューサー
今年も力作ぞろいで選ぶのが悩ましかった。テーマを作品に落とし込み、それぞれの主張が感じられた。その中でインパクトのあるものが選ばれたのではないかと思う。
デザイン部門では、デザイン画と実際に作られたものにイメージのギャップがあり絵と実物を見比べながらの選考だった。その中で、小学2年生の作品が大賞に選ばれたが、庭そのものの形を菓子にデザインした作品は、デッサン力は小学生のものだが実景が目に浮かぶようで、職人が実作した菓子は作者の思いが表現され心動かされた。
実作部門は、どれも店頭に並んでいてもおかしくないような出来栄えで応募される方のレベルの高さが感じられた。その中で大賞に選ばれた作品は、実物を見た時にシンプルな形ながら存在感があった。味は上品で栗とバニラの香りがほどよく広がり後口もよかった。
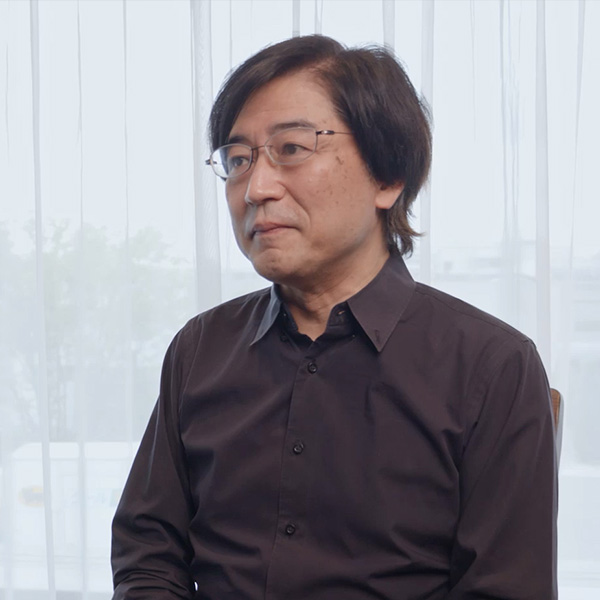
暦本 純一ソニーコンピュータサイエンス
研究所 CSO
今年も力作ぞろいで選ぶのが悩ましかった。テーマを作品に落とし込み、それぞれの主張が感じられた。その中でインパクトのあるものが選ばれたのではないかと思う。
デザイン部門では、デザイン画と実際に作られたものにイメージのギャップがあり絵と実物を見比べながらの選考だった。その中で、小学2年生の作品が大賞に選ばれたが、庭そのものの形を菓子にデザインした作品は、デッサン力は小学生のものだが実景が目に浮かぶようで、職人が実作した菓子は作者の思いが表現され心動かされた。
実作部門は、どれも店頭に並んでいてもおかしくないような出来栄えで応募される方のレベルの高さが感じられた。その中で大賞に選ばれた作品は、実物を見た時にシンプルな形ながら存在感があった。味は上品で栗とバニラの香りがほどよく広がり後口もよかった。
いずれにしても細かいところまでこだわりがあって惹かれる作品が多くあり審査は悩ましかった。

濱崎 加奈子有斐斎弘道館 館長
茶の湯とともに発展した京菓子のテーマとして、後世に大きな影響を与えた二人の茶人(実際には茶人としてだけでなく多才な方々ですが)をとりあげました。およそ400年前の茶人の美意識を読み取り、現代の茶席菓子として表現する試みに対し、多くの方に挑戦いただけたことを嬉しく思います。二人が残した作品や記録を探究し、また二人の関係性を新たに解釈するものもありました。寛永の時代は、身分やジャンルを超えた多様な人々が集い、綺羅星のごとくスターが誕生しました。菓子を通して、寛永文化の空気を感じていただければ幸いです。